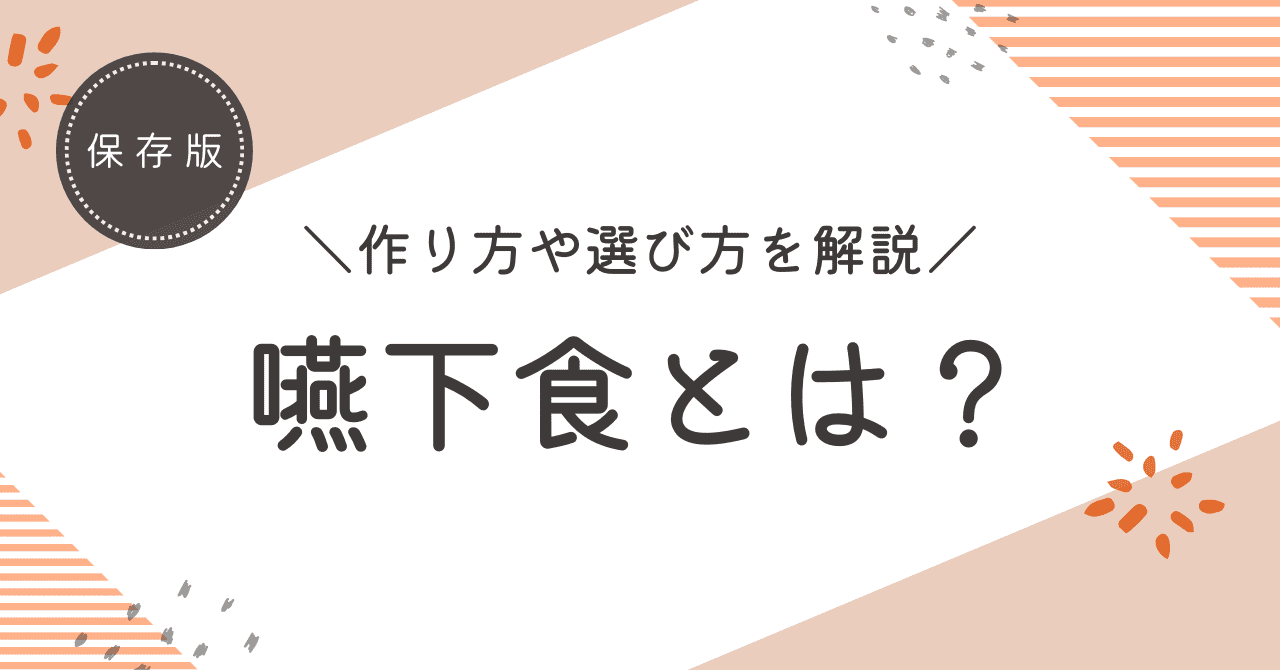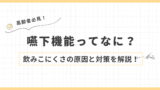最近、食事でむせるようになってきたけど、どうすればいいのかしら・・・

食事中のむせは食欲や食事量の低下に繋がりやすく、高齢者や持病をお持ちの方の大きな問題となっています。
上手に調理して安全に美味しく食べるためのポイントを解説していきます!
「最近むせこみが多くなってきた」「高齢の親が普通のご飯を食べにくそうにしている」「嚥下障害がある家族にどういう食事を作ればいい?」と悩んでいませんか?
高齢者や嚥下機能が低下した方にとって、食べ物を安全に飲み込むことが大きな課題になります。嚥下食ややわらか食を上手に取り入れることで、誤嚥リスクを軽減しながら栄養不足を防ぎ、食事の楽しみを保つことができます。
本記事では、軟飯から全粥、刻み食やムース食まで、食事形態の調整について詳しく解説します。
嚥下食・やわらか食とは?基本の考え方
嚥下食(えんげしょく)とは、高齢などによって飲み込む力が衰えた人に合わせて食材のとろみ、食感、形態を調整した食事です。嚥下訓練食も含め嚥下食と呼ばれています。
嚥下機能に問題がある方が嚥下食を利用することで、安全に・スムーズに栄養を摂取することができ、誤嚥性肺炎や栄養不足を防ぐことができます。
高齢者の嚥下機能については以下の記事で解説していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください!
嚥下食の種類
嚥下のレベルによって、以下のように嚥下食を5段階に分類しています。
0から5に数字が大きくなるにつれで、嚥下の難易度が高くなります。
0j:嚥下訓練食品 スライス状のゼリー
- 均質で、付着性が低く、凝集性が高く、硬さが柔らかく、離水が少ないゼリー・スライス状のもの
0t:嚥下訓練食品 ゼリー
- スプーンですくった時点で適切な食塊状となっているもの
- 中間から濃いとろみがあるもの
1j:嚥下調整食 ゼリー・プリン・ムース
- 咀嚼する必要がなく、スプーンですくった時点で適切な食塊状となっているもの
- 例:卵豆腐や、おもゆやミキサー粥の物性に配慮したゼリー、介護職として市販されているゼリーやムース
2:嚥下調整食 ミキサー・ピューレ・ペースト食
- スプーンですくって、口腔内の簡単な操作により適切な食塊にまとめられるもので、送り込む際に多少意識して口蓋に舌を押しつける必要があるもの
- 調整方法としては、食品をミキサーにかけてなめらかにし、かつ凝集性をつけたもの
- 例:とろみ付けしたおもゆ、付着性が高くならないように処理をしたミキサー粥
3:嚥下調整食 やわらか食・ソフト食
- 形はあるが,歯や補綴物がなくても押しつぶしが可能で、食塊形成が容易であり、口腔内操作時に多量の離水がなく、一定の凝集性があって咽頭通過時のばらけやすさがないもの。やわらか食,ソフト食などといわれていることが多い
- 例1:市販の肉・魚や野菜類を柔らかくさせた製品の多くも、この段階に含まれる
- 例2:水分がサラサラの液体でないように配慮した三分粥、五分粥、全粥など
4:嚥下調整食 全粥・軟飯・軟菜食
- 誤嚥や窒息のリスクのある嚥下機能および咀嚼機能の軽度低下のある人を想定して、素材と調理方法を選択した嚥下調整食
- かたすぎず、ばらけにくく、貼りつきにくいもので、箸やスプーンで切れるやわらかさ
- 例1:全粥や軟飯
- 例2:素材に配慮された和洋中の煮込み料理、卵料理など

なんとなくわかるけど、どの段階が自分に合うのか、そもそもどうやって作るのかわからないという方は多いのではないでしょうか。
次からは、実際の調整方法について説明していきますね!
ご飯の柔らかさ調整
| 種類 | 目安と作り方 | 合う嚥下レベル |
| 軟飯(なんはん) | ・米1合に対し、通常より+50〜100mlの水 ・米粒の形は残っているが、箸やスプーンで簡単に潰せる | ・軽度の噛む力・咀嚼力低下がある方 |
| 全粥(ぜんがゆ) | ・米1合に水4〜5倍で炊き、米粒が柔らかく形が残る程度 ・炊飯器のおかゆモード or 鍋で煮る | ・軟飯だとむせやすい方、またはもう少し柔らかいご飯が必要な方 |
| 七分粥・五分粥 | ・七分粥:米1合に対して水7倍前後 ・五分粥:米1合に対して水10倍前後 ・米粒が潰れ気味で、ほとんど噛まずに飲み込める | ・全粥だとむせやすい方 ・中等度の嚥下障害や噛む力がかなり弱い場合 |
| ペースト粥 | ・全粥以上に煮込んだ後、ミキサーで完全にペースト状に | ・七分粥だとむせやすい方 |
| 酵素入り粥 | ・全粥以上に煮込んだ後、酵素入りゲル化剤を入れてミキサー状に | ・ペースト粥が口や喉に引っ付いてしまう場合 |
おかずの大きさ・柔らかさ調整
| 種類 | 目安と作り方 | 合う嚥下レベル |
| 一口食 | ・おかずを一口大に切る ・必要に応じて出汁とろみをかける | ・軽度の噛む力・咀嚼力低下がある方 |
| 刻み食 | ・おかずを細かく刻む ・必要に応じて出汁とろみをかける | ・噛む力が弱い方 ※嚥下機能が低下していたり、唾液の量が少ない人には向かないため注意が必要 |
| ソフト食 | ・茹でたり煮込んだりする時間を長くして柔らかくする ・圧力鍋などを使うとより柔らかくなる ・食材によっては柔らかくした後に、フードプロセッサーやすり鉢などを使って細かくすり潰す | ・噛む力だけではなく、飲み込む力も弱くなっている方 |
| ミキサー食 | ・調理した食材に水分を加え、ミキサーにかけてとろとろにする ・必要に応じてとろみ剤や出汁とろみ、ソースなどとろみのあるものを加える | ・ソフト食でもむせてしまう方 |
| ムース食 | ・すり鉢や裏漉し器、フードプロセッサーやミキサーを使い、食材をなめらかにする ・必要に応じて出汁などの水分を加える ・とろみ剤を加え、再度ミキサーにかける ・時間をおけばムース食となる | ・ミキサー食でもむせてしまう方 |
水分のとろみの目安と調整方法
とろみの目安
| 種類 | 目安と作り方 | 合う嚥下レベル |
| 薄いとろみ | ・ストローで容易に吸うことができ、スプーンを傾けると、すっと流れ落ちる | ・普通の水分や汁物でむせてしまう方 |
| 中間のとろみ | ・ストローで吸うのは抵抗があり、スプーンを傾けると、とろとろと流れる | ・薄いとろみでもむせてしまう方 |
| 濃いとろみ | ・明らかにとろみがついており、ストローで吸うことはできない ・スプーンを傾けても、ある程度形状が保たれ、流れにくい | ・中間のとろみでもむせてしまう方 |
とろみの付け方
- 飲み物を救い上げるようにスプーンで前後にかき混ぜながらとろみ剤を加える
- 数分おく
- ダマができた場合は、取り除く
- とろみの状態を確認する
「作るのは大変…」宅配弁当も選択肢
調理が難しい時の解決策
- やわか食、ムース食対応の宅配弁当サービスを活用すれば、栄養と安全を両立しやすい
- 嚥下食や介護食に特化したコースや管理栄養士監修のメニューもある
メリット
- 完成した商品を自宅まで届けてくれるため、買い物や調理の負担が軽減
- 誤嚥リスクが高い人向けのソフト食コースなど選択肢が豊富
- 家族が遠方に住んでいてもオンラインで注文管理ができる
デメリット
- 自炊よりも割高になりやすい
- 味や硬さの好みと合わない場合がある → お試しセットがある場合はそちらで確認
まとめ
- ごはん、おかず、水分のとろみ調整の3つを組み合わせれば、高齢者や嚥下障害のある方でも安全に食事を楽しめる
- 作るのが大変な時は、宅配弁当や市販の介護職を取り入れ、栄養と手間のバランスをとる
- 専門家(医師、歯科衛生士、言語聴覚士)に相談しながら、自分に合った”嚥下食”を選んでください

嚥下食は、飲み込みが難しくなってきた方の生活を支える重要な手段です。
調理や食材選びが負担に感じる方は、宅配弁当や市販の介護食という選択肢もぜひ検討してみてください。
安心・安全な食事で食べる喜びを諦めず、健康寿命を伸ばしていきましょう!
参考文献
・Logemann JA. Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. 2nd ed. PRO-ED; 1998.
・Bauer J, Biolo G, Cederholm T, et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):542–559.
・日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会:日摂食嚥下リハ会誌. 2013;17(3):255–67.