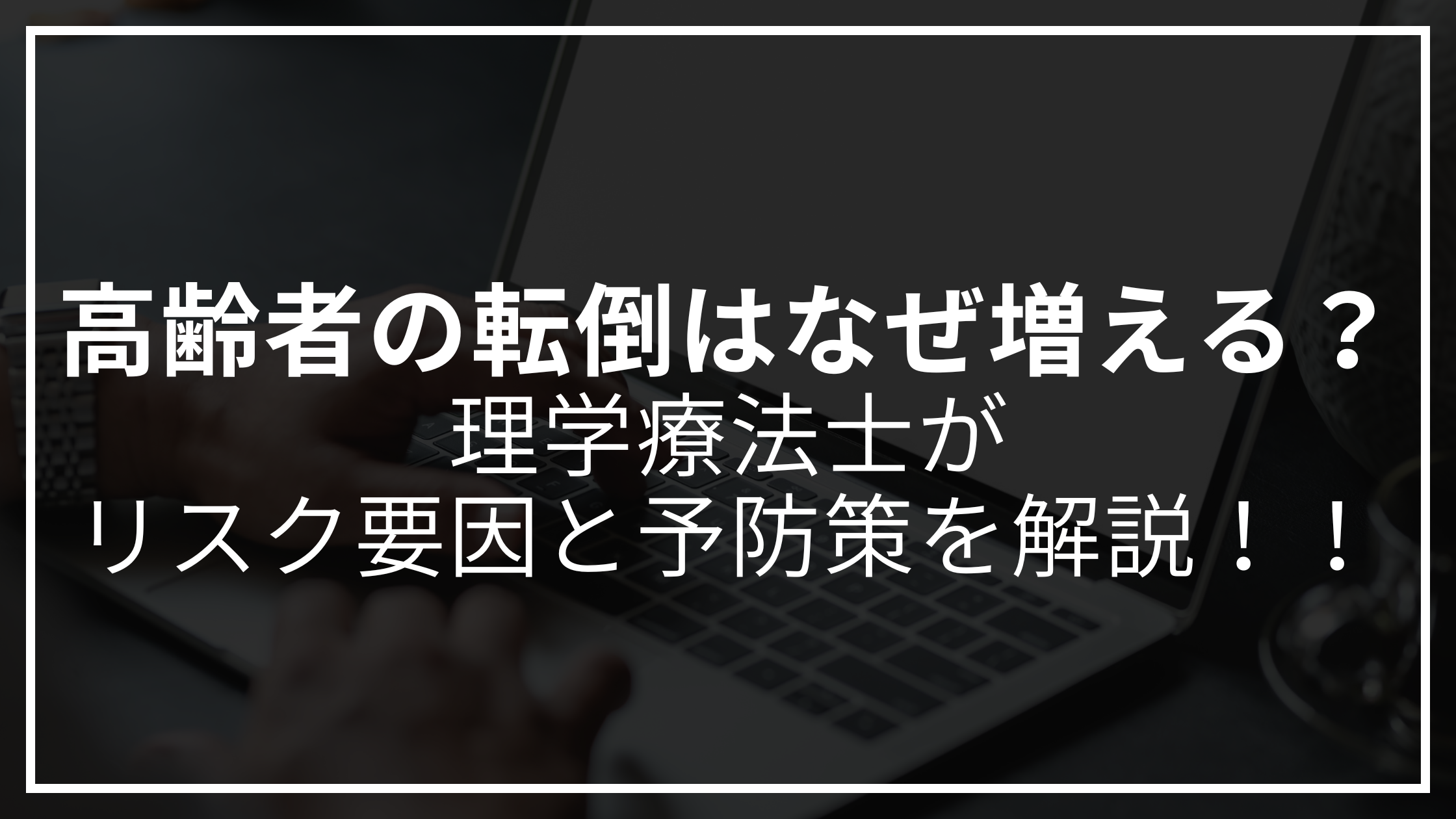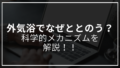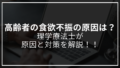「最近、うちの親がよくつまずいているみたいだけど、放っておいて大丈夫かな?」「高齢者の転倒ってそんなに多いの?」「どうしたら転倒を防げるの?」
そんな不安を感じている方いませんか?
実は、転倒は高齢者にとって大きなリスクであり、骨折や要介護につながる重要な問題です。今回は、理学療法士の視点から、転倒の実態やリスク要因、そしてご家族ができる予防策をわかりやすくお伝えします。
高齢者の転倒の現状
毎年、約3割の高齢者が転倒を経験
まず、高齢者の転倒がどれほど頻繁に起こっているのか、データを見てみましょう。
世界保健機関(WHO)によると、65歳以上の高齢者のうち約28〜35%が毎年少なくとも1回は転倒を経験するとされています。みなさんが相像しているより多いのではないでしょうか。
また、年齢がさらに上がると、その割合は一段と高くなることがわかっています。
転倒がもたらす深刻な影響
「骨折なんて稀なんじゃないの?」と思う方も多くいるのではないでしょうか。
実際には、骨折や頭部外傷などの重大なケガに直結する場合が多くあります。特に高齢者で多いとされる大腿骨近位部骨折(股関節周辺の骨折)は寝たきりや要介護状態へ移行するリスクを高めてしまいます。
実際の研究でも、転倒は高齢者の生活機能を大きく損なう原因の1つとされており、転倒の予防や対策が重要とされています。
高齢者が転倒しやすい理由とリスク要因
高齢者の転倒には、さまざまな要因が複合的に関わっています。大きく分けると、身体的要因・環境的要因・心理的要因に分類できます。
身体的要因
- 筋力・バランス能力の低下
・加齢に伴う筋肉量(いわゆるサルコペニア)と筋力の低下が、歩行や立ち上がり動作を不安定にします。
・足首や膝周りの筋力が弱くなると、ちょっとした段差でもつまずきやすくなります。 - 視覚や感覚機能の低下
・白内障や緑内障などの影響で足元が見えづらくなり、転倒リスクが高まります。特に夜にトイレに行くときに転倒してしまう高齢者は少なくありません。
・耳の三半規管や神経系の衰えでバランスを取りにくくなることも。 - 持病や服薬の影響
・高血圧、糖尿病、心疾患などの持病があると、めまいや全身のだるさでふらつきやすくなる場合があります。
・一部のお薬には、副作用として立ちくらみを起こすものや眠気が出るものがあるので要注意です。
環境要因
- 住宅内の段差や照明不足
・廊下やトイレ入り口などのちょっとした段差が、つまずきの大きな原因に。
・夜間の移動時に照明が暗いと、足元が見えず転びやすくなります。 - 生活動線(歩く経路)の乱れ
・部屋の中に物が散乱している、コードが足に引っかかるなどの障害物は、転倒の原因に。
・手を添えると動いてしまう家具にもたれ掛かったり、支えにしようとして転倒してしまうこともあります。 - 外出先の歩道や階段
・歩道の段差、雨の日の濡れた路面、急な階段など、屋外の環境も高齢者にとっては大きなハードル。
・人混みの中で歩くことも転倒のリスクになるかもしれません。
心理的要因
- 転倒恐怖
・過去に一度転倒すると、「また転んだらどうしよう」という恐怖感が強くなる傾向があります。
・この恐怖によって活動量が減り、さらに筋力やバランス能力が低下する悪循環に陥ることも。 - 自信損失・抑うつ状態
・年齢を重ねるごとに身体機能が低下すると、自信を失いがち。
・うつ状態で集中力が低下し、周囲への注意が行き届かなくなる場合もあります。
「うちの親は大丈夫?」チェックリスト
ご家族が、親御さんの転倒リスクをざっくり把握できるようにチェックリストを作ってみました。
3つ以上当てはまったら要注意です。
- 最近、よくつまずいたり、歩行スピードが極端に遅くなった
- 「めまいがする」「フラつく」と本人が口にしている
- 服用している薬が増えて、種類が多くなっている(ポリファーマシー)
- 家の中の段差や手すりの有無について、見直したことがない
- 日常的に外出や運動をあまりしない・週1回以下しか外出しない
- 1年間以内に転倒したことがある
- 片足で立ったまま靴下をはくことができない
- 手すりにつかまらないと、階段の昇り降りが不可能
- 物忘れが気になる
- 目が見えにくい
- 耳が聞こえにくい
当てはまる項目が多いほど、転倒リスクが高い可能性があります。自宅でできるエクササイズなどを取り入れ、健康寿命を伸ばしていきましょう!
転倒リスクを減らすための基本対策
生活環境の見直し
- 段差解消や手すりの設置
トイレや浴室、階段など、転倒しやすい場所に手すりを取り付けることで安定感が増します。 - 足元照明やセンサーライトの活用
夜間のトイレ移動や玄関先が真っ暗だと危険度がアップ。小さなライトを設置してあげましょう。
身体機能の維持・向上
- 趣味活動の継続
好きなことなら無理なく続けられますよね。また人との関わりも大切。趣味活動を通じて、活動量を維持しましょう。 - 散歩や体操
1日5000歩を目安に歩きましょう。まずは無理のない時間から始め、徐々に歩く距離を増やしていくことが大切です。
服薬内容の確認
- 薬剤師や医師に相談し、副作用や重複処方をチェック
複数の医療機関にかかっているうちに、同じような薬が何種類もでていることも。またお薬はたくさん飲むとポリファーマシーといってフラつきの原因になることも。
転倒を検知するデバイスの導入
- スマートウォッチや緊急通報サービス
絶対に転倒しない!なんてことができればいいですが、難しいのも現実。万が一転倒してしまった時に、自動的に家族やコールセンターへ通報してくれる機能がある商品も増えています。
まとめ
高齢者の転倒は、身体的要因(筋力低下、視力障害など)、環境的要因(段差、照明不足など)、そして心理的要因(転倒恐怖、抑うつなど)が複雑に絡み合って発生します。
もしご家族の中に「最近よくつまずく」「活動量が減った」という方がいらっしゃるなら、ぜひ今回のチェックリストや対策を参考に、まずは生活環境の整備や適度な運動から始めてみてください。
転倒を一度でも経験すると、恐怖感からさらに外出や運動を控えてしまう人も少なくありません。
ですが、適度に身体を動かすことこそが、転倒の負の連鎖を断ち切る重要なカギです。
ご家族が早めに対策を講じることで、大切な方の安全と生活の質を守ることができるかもしれません。
本記事をきっかけに、転倒リスクの把握と予防への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。次回は、理学療法士の視点から自宅でできる簡単な転倒予防エクササイズを紹介する予定です。ぜひ、そちらもあわせてご覧ください。
参考文献
Yoshida S. A Global Report on Falls Prevention: Epidemiology of Falls. World Health Organization; 2007.
Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med. 1988;319(26):1701-7.
American Geriatrics Society, British Geriatrics Society. Clinical Practice Guideline for Prevention of Falls in Older Persons. 2010.